当院循環器内科は平成4年4月に設立され、現在は、心臓、大動脈及び末梢血管の疾患を専門に診療を行っています。主な対象は、心不全、狭心症、不整脈、心臓弁膜症、心筋症等の心臓疾患や大動脈、肺動脈、四肢動脈等の血管疾患です。また、これらの疾患の原因となる高血圧や高脂血症等の生活習慣病の早期介入や予防にも取り組んでいます。
診療のご案内[PDF]
※当科、診療のご案内は上記からご覧いただけます。
心不全とは、心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気です。その原因は、血液を充満させ全身に駆出する心臓の主たる機能に何らかの障害が生じたためです。代表的な病気は、高血圧、心臓の血管の病気(冠動脈疾患)、不整脈(心房細動など)や大動脈弁等の弁の病気などですが、さまざまな要因で生じます。また、近年国民の高齢化とともに癌疾患と並んで、心不全は増加しています。ところが心不全の5年生存率は約50%で、癌疾患の60%余りに比較して心不全の方が低いことが知られており、この改善に向けて取り組む必要性があります。
北九州、特に八幡東区を中心とした地域は、全国的にも高齢化が進んでいます。この高齢化社会において危機感を抱いている課題は、心不全リピーターの増加です。この数年の傾向としては、急性心不全の入院患者(65歳以上の高齢者)のうち、5割強がリピーター症例でした。また、そのうちの6割が独居もしくは高齢者二人世帯でした。心不全の原因は多岐に渡りますが、高齢者の於かれた社会的背景にも問題が潜んでいます。そうした背景を踏まえ地域全体で患者さんを支援するため、当院では心不全センターを設立しました。
当院では、心臓リハビリテーションの強化を図っています。心臓リハビリテーションは包括的ケアを骨子にしており、特に運動療法は薬剤抵抗性難治性心不全にも効果が期待できます。重症者や高齢者にも安全にリハビリを導入するために、全例で心肺運動負荷試験(CPX)を施行しています。
動脈硬化は、全身性疾患であり、下肢動脈や腎動脈も好発部位です。間歇性跛行のような症状に対しては、ABI検査や血管エコー検査を行い、動脈硬化の広がりや程度を診断します。症状がかなり進行している場合は、カテーテル治療を行います。また、下肢動脈については、血管外科での治療を必要とする場合もあります。
徐脈性不整脈に対しては、ペースメーカー植え込み術を行っています。さらに、頭部、胸部、腹部、下肢等ほとんどのMRI検査が可能なペースメーカーを利用できるようになりました。当院は、このペースメーカーでMRI検査を行うための認可を受けており、メドトロニック社とセントジュード社のMRIペースメーカー使用患者に対してMRI検査が可能です。
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |||
| 外来 | 外来患者延べ数 | (名) | 3,422 | 2,686 | 2,810 |
| 初診患者数 | (名) | 454 | 257 | 464 | |
| 再診患者数 | (名) | 2,968 | 2,429 | 2,346 | |
| 1日平均外来患者数 | (名) | 14.1 | 11.1 | 11.6 | |
| 入院 | 新入院患者数 | (名) | 119 | 60 | 262 |
| 退院患者数 | (名) | 113 | 64 | 241 | |
| 入院患者延べ数 | (名) | 2,239 | 1,086 | 3,966 | |
| 1日平均在院患者数 | (名) | 6.1 | 3.0 | 10.9 | |
| 平均在院日数 | (日) | 18.3 | 16.5 | 14.9 | |
| 紹介 | 紹介率 | (%) | 72.7 | 67.7 | 102.7 |
| 逆紹介率 | (%) | 208.8 | 234.6 | 276.7 | |
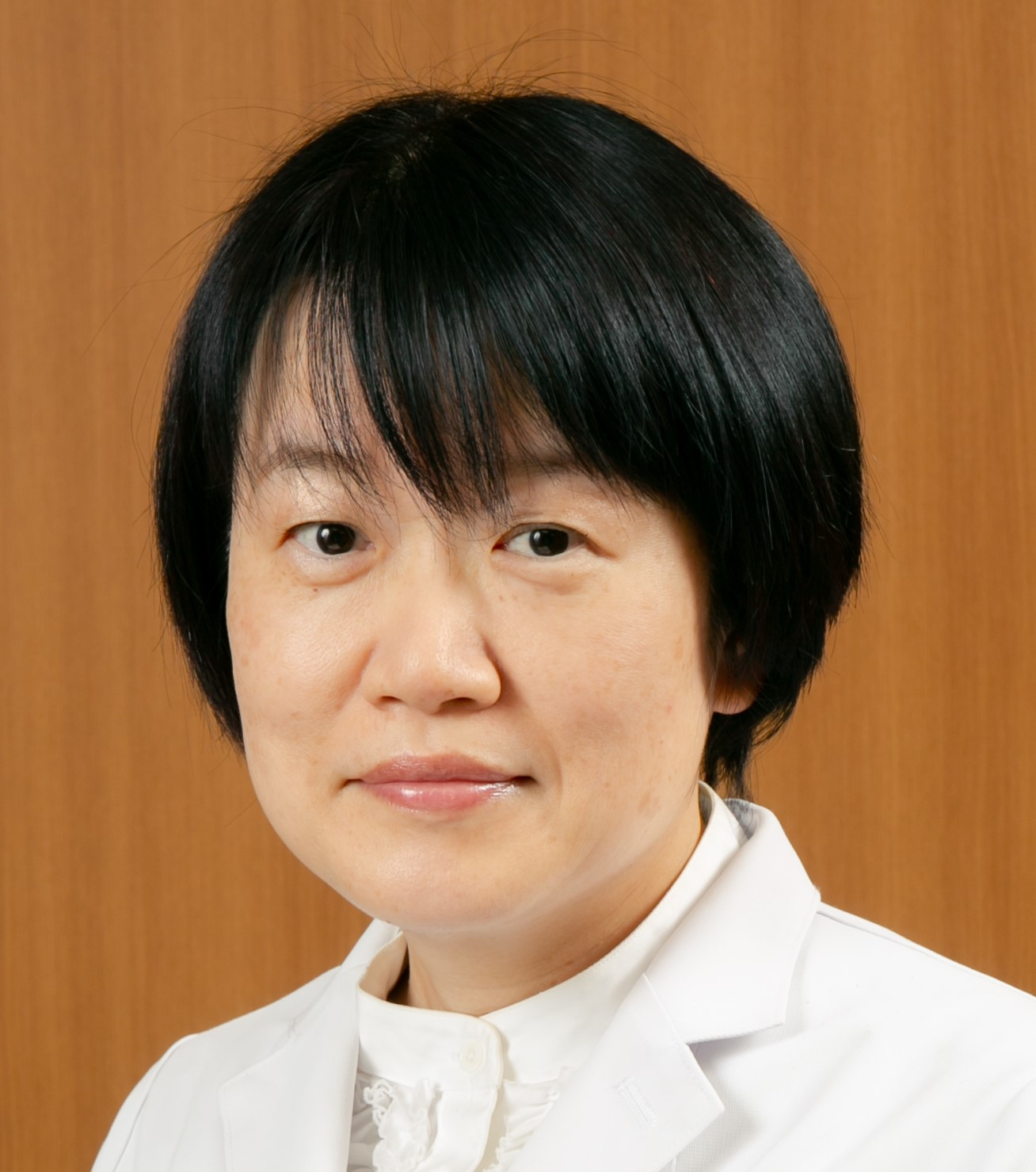
| 専門分野 | 内科・循環器内科一般 |
|---|---|
| 学会関係 |
|
| コメント | 産業医科大学 平成5年卒 |

| 専門分野 | 内科・循環器内科一般 |
|---|---|
| 学会関係 |
|
| コメント | 産業医科大学 平成23年卒 |

| 専門分野 | 内科・循環器内科一般 |
|---|---|
| 学会関係 |
|
| コメント | 宮崎大学 平成28年卒 |
当院は少人数で外来とカテーテル検査や治療、救急医療を行っているため、外来は午前中の時間枠しかとれません。このため再診に関しては原則予約制としています。新患はこの限りではありませんが、紹介状や連携室への情報提供があると助かります。
ペースメーカー外来(月曜日)では、当院でペースメーカー治療を行った患者さんの経過観察を行っています。